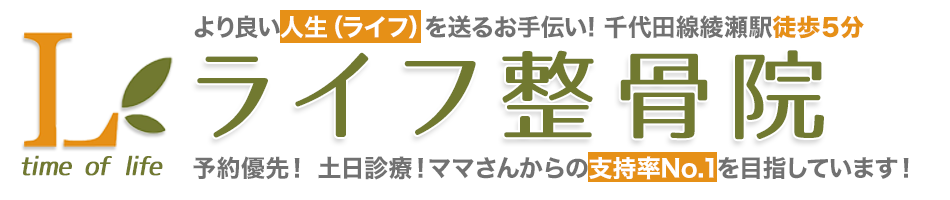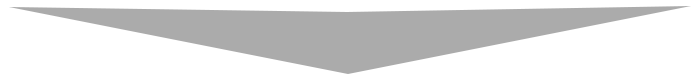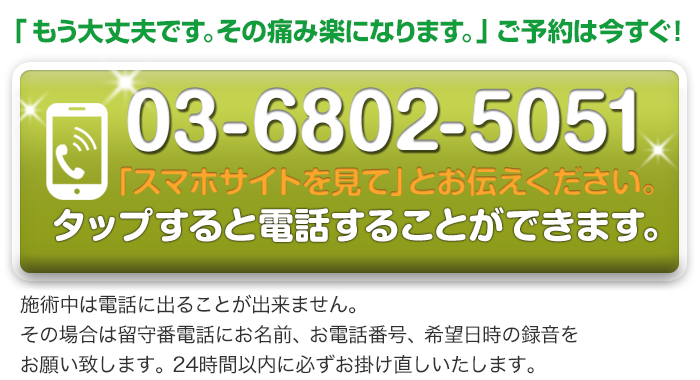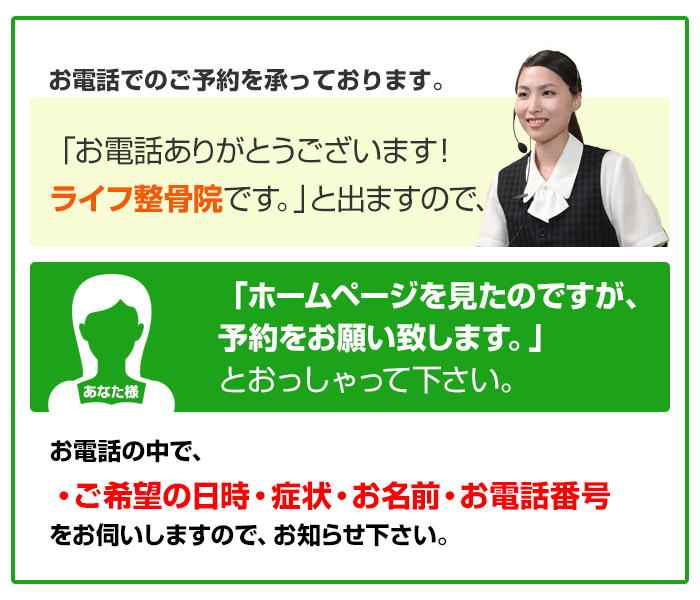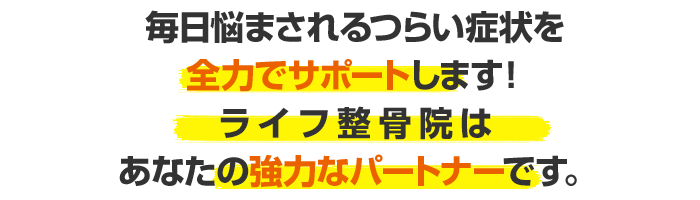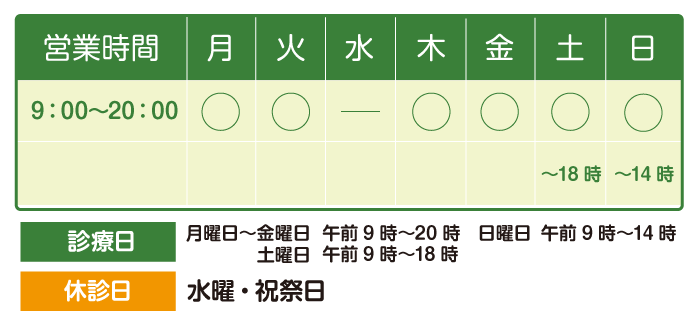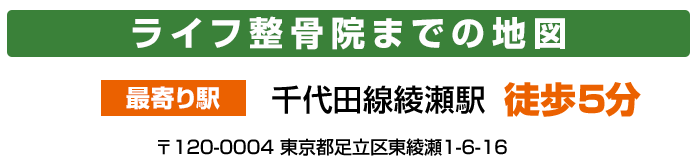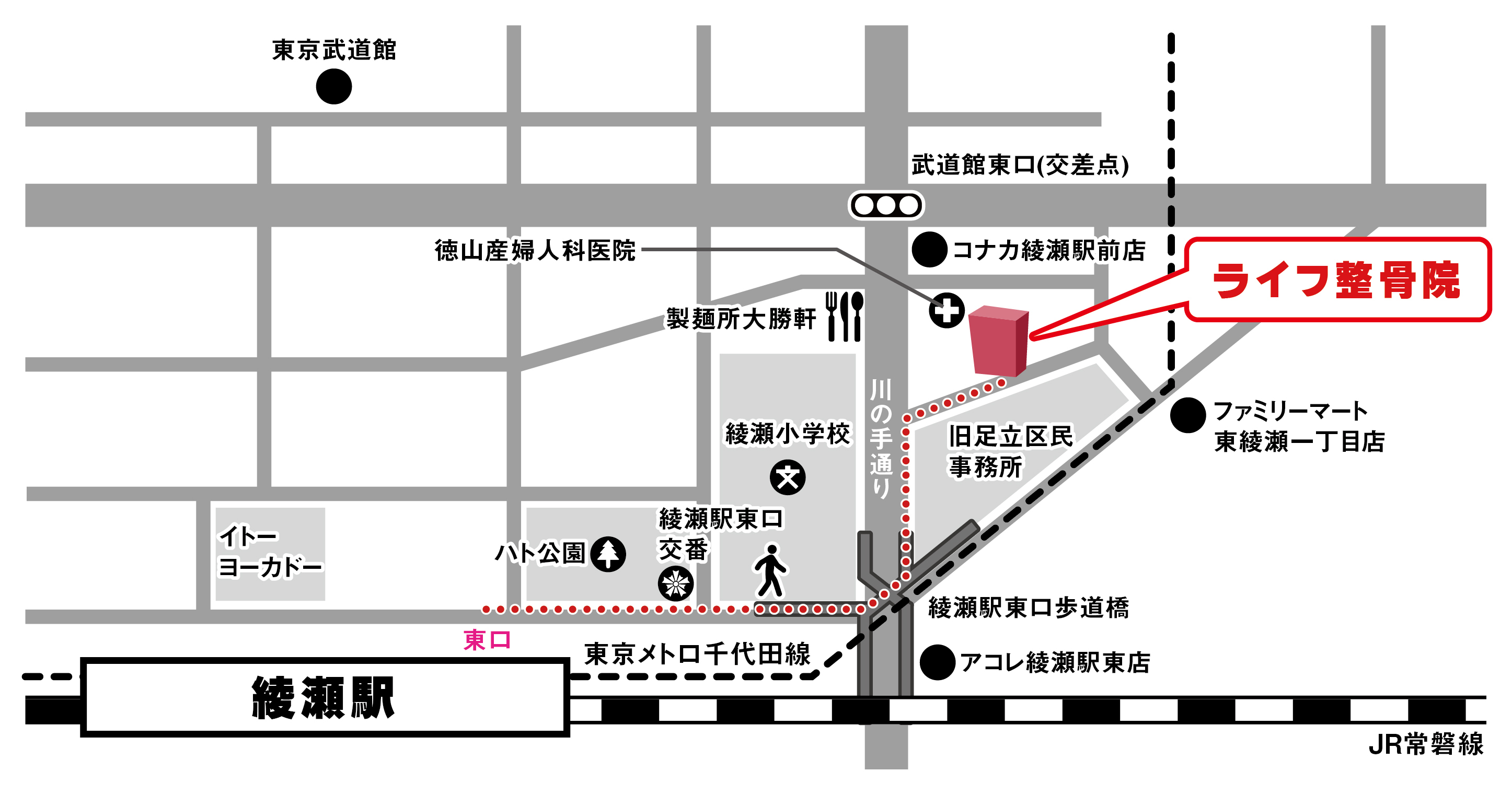女性は、生理の周期によって、1カ月の間にホルモンのバランスが大幅に変わります。
生理前から生理中にかけて、眠気が強くなる、1日中眠い日が増えるのもまた、ホルモンの変化による現象です。
排卵後から生理直前までの黄体期と呼ばれる期間には、女性ホルモンの一種である「プロゲステロン」の分泌が盛んになります。
このプロゲステロンには、眠気を強くする作用があるため、プロゲステロンが多く出る黄体期には、眠たい、ぼーっとするなどの症状が現れやすくなります。
実際に妊娠すると、体が熱っぽくなったり、眠い日が続くことなどが知られていますが、これは妊娠によってプロゲステロンの分泌が増えるためです。
妊娠しなくても、生理の周期によってプロゲステロンの分泌が増加することで、生理前から生理中に眠くなる人はたくさんいます。
ところが一方で、この黄体期に寝付きの悪さに悩む人もいます。
実は黄体期は、日中は眠気に襲われやすく、夜間には寝付きが悪くなりやすいという難しい時期でもあるのです。
私たちの体は、体温を下げながら寝付く仕組みになっています。
この体温調節がうまくいかないと、眠いのに寝付けないという睡眠障害が起こりやすくなってしまいます。
黄体期は、基礎体温の高温期にあたる時期です。
体温の変動が少なく、基礎体温が高い状態が保たれるこの時期には、入眠時の体温が下がりにくいことで、寝付きの悪さにつながるケースが多くなります。
中には夜中に何度も目覚めてしまい、熟睡できない人もいます。
このように、女性ホルモンの変動は、睡眠のサイクルや睡眠の質に大きく関係しています。
生理前や生理中には、どんなに寝ても眠気がとれなかったり、しっかり休んだはずなのに体がだるくてしんどい日もあるでしょう。
そんな時はできる限りペースダウンして、ゆっくりと過ごす時間を設けてあげることも大切です。
この不調がホルモンによる影響であることを知っておくことで、頑張りすぎを防ぐ意識にもつながっていくはずです。
ホルモンの変動による体の変化をどう受け入れるかで、毎月のストレスも変わってくると思います。
また、眠気の感じ方には個人差もあるので、あまり他人と比べずに、自分の体に起きている変化をありのまま受け入れてあげることで、気持ち的にも少しは楽になれるかもしれません。